独自経済圏の創出に動き出したりそなHD~金商連携の加速の意義~
こんにちは。
浦和の民です。
本日はこちらの話題
一部引用します。
しかし、りそなグループはpringとの接続をユーザーの選択肢として加えつつも、別途独自のキャッシュレス経済圏をつくり出す動きを見せている。
同グループは8月30日、小売・飲食店などの加盟店を対象に、QRコード決済やクレジットカード、交通系ICカードなどに対応する決済端末を無償で提供するとともに、ユーザー向けのウォレットアプリも提供すると発表した。大手行としては初の取り組みとなる。
加盟店側は、無償で端末の提供を受けることで、現金管理・決済コストを削減し、レジ周りを簡素化できる。また、売上金(5営業日前の決済分)を毎日受け取ることができるため、月に1、2度まとめて入金される一般的なクレジットカード決済に比べ、資金繰りを安定させることができる。
ユーザー側は、銀行口座と直結したスマホ決済サービス「りそなPay」のほか、口座からの後払いやおつり貯蓄、クーポンやポイントの管理・利用、家計簿アプリと連動する電子レシートなどさまざまな便利機能を、一つのウォレットアプリで簡単に使うことができるようになる。
ついに金融機関が『個人向け』と『加盟店向け』のキャッシュレスソリューション提供に乗り出してきました。
1.なぜ、銀行がキャッシュレスを推進するのか
銀行がキャッシュレスを推進する理由は大きく二つあると考えられます。
1つ目は、いわずと知れたコスト削減の観点です。
消費者からすれば現金は銀行やATMどこでも引き出すことができますが、それに対応するための、計数、運搬、保管等に銀行は莫大なコストを支払っています。
キャッシュレスになれば、データのやり取りだけで銀行取引の全てが完結しますので、実店舗やATMで行っていた作業が不要になります。極論から言えば、実店舗は不要になるかもしれません。
そうなれば、人件費、物件費等のコストの大幅な削減が実現可能となります。
2つ目は、データ分析・提供による新たな収益源創出の観点です。
前述の通り、データのやり取りが増加すれば、金流データを多く取得できれるため、そこに商流のデータを組み合わせることによって、顧客(=消費者)がどのような人物なのかがよりクリアに分かるようになります。
そこで得られたデータを基に、金融サービスのレコメンドや、有償で外部への情報提供等を通した収益増加を見込んでいると想定されます。
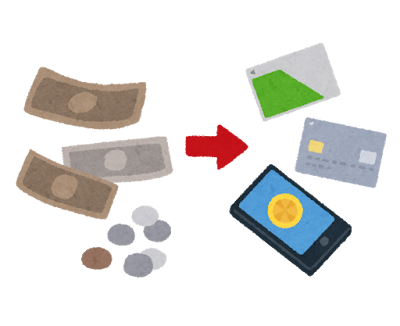
2.キャッシュレス化への課題を解決するためのアプローチ
銀行にとってメリットのあるキャッシュレス化を推進するためには、ハードルがあります。それは店舗側の対応です。
小売店に出向いた際に自分が持っているクレカ、電子マネーが使えない・・・といった苦い経験を皆様もお持ちだと思います。
そうです、個人がせっかくキャッシュレスへのモチベーションを上げても、使えない加盟店が多ければ現金決済はなくなりません。
そこで、今回りそなHDは決済端末を無償で提供し、且つ加盟店が支払う手数料を通常(3%程度)より低減することで、加盟店側の導入のハードルを下げる方向に動きました。
これによって、使える店舗を爆発的に増やし、得られるデータを増やそうという狙いだと筆者は考えます。
3.サービス普及に当たっての課題
ネット系金融機関を除けば初めての取組を行うりそなHDですが、課題もあると考えます。
それは加盟店開拓への行員のモチベーション向上です。
このビジネスモデルで収益が計上されていくのは決済データを分析・外部提供する本部担当部署になります。加えて、データが蓄積されるには相応の時間がかかるため、短期で結果を出さなければいけない営業店担当者にとって、加盟店開拓のプライオリティは低くなることが予想されます。
りそなHDとしては、この施策に対する明確なインセンティブ設計(例えば、一件開拓毎にみなし収益○○万円 等)を行い、加盟店開拓へのモチベーションを上げることが必要となるでしょう。
もし、現場任せの施策となった場合は名ばかりのサービスに成り下がる可能性もあります。そのため、今後の成り行きを見守りたいと思います。
長くなりましたが、本日はこれまで。
関係しそうな記事も貼っておきます。